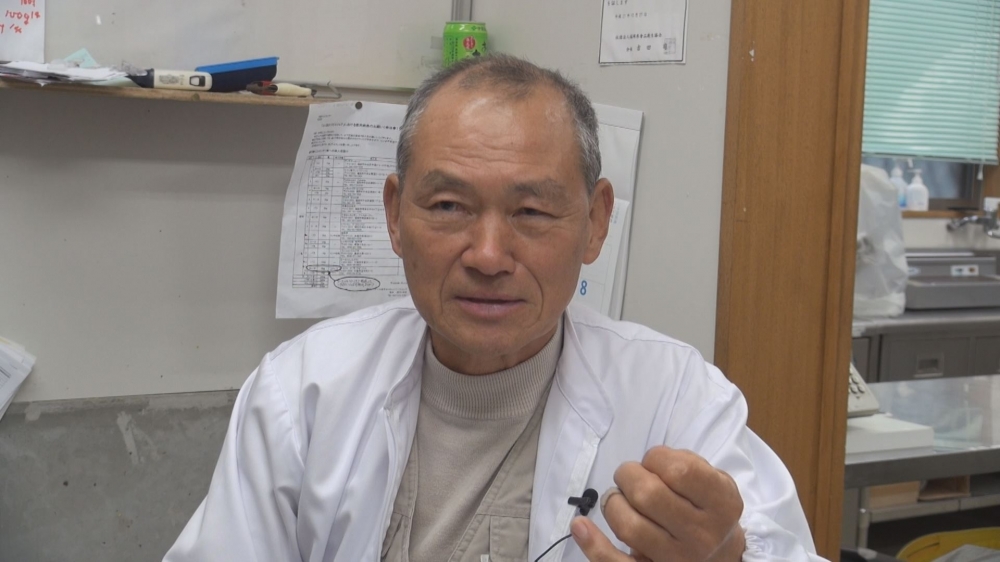これまでの放送内容 -テレビ西日本(TNC)-
2014年4月6日(日)
美味山くじら 厄介者のイノシシを特産品に
イノシシの肉を新たな特産品として売り出し、農作物被害額の穴埋めにつなげようと地元猟師や専業農家、会社員らが1から立ち上げた「浮嶽山くじらセンター」に密着です。
▼福岡県糸島市は、ここ数年、イノシシが稲などを食い荒らす被害に見舞われています。農家にとってイノシシは害獣。糸島市農業振興課によると、イノシシによる農作物への被害は2011年度、約3200万円にのぼります。アナグマ(約290万円)やニホンザル(約260万円)などと比べて桁違いに高い金額です。また被害作物は稲がトップ。次いで果樹、野菜、タケノコ、イモなど、あらゆる農作物に広がっています。過疎化による農作放棄地の増加や、狩猟だけで生活がなりたたないため、県内の狩猟者が激減していることからイノシシが増加し、被害が広がっているのが現状です。▼肉処理加工所「浮嶽くじらセンター」。捕らえたイノシシの精肉作業所です。イノシシの肉を新たな特産品として売り出し、被害額の穴埋めにつなげようと地元猟師や専業農家、会社員ら14人で立ち上げました。肉は臭みもなく、ヘルシーで、スキヤキ、しゃぶしゃぶなどの料理が美味。ハムやソーセージなどに加工して販売も始め、町おこしの一環となるべく期待を寄せます。イノシシハンターに密着しました。
制作局:テレビ西日本(TNC)

2014年1月26日(日)
木を継ぐ
▽日本各地に残る伝統的な木造建築。その技を受け継ごうと日々、木と向き合う職人が福岡にいる。今回、彼らが挑むのは400年以上続く寺の本堂の新築工事。
▽日本各地に残る伝統的な木造建築をまもるために日々、木と向き合う職人たち。今回、彼らが挑むのは400年以上続く寺の本堂の新築工事。最大で1.5トンという巨大な柱を幾本も使い、難工事に挑む。そこで駆使されるのは、木と木を組み合わせる「継手(つぎて)」や「仕口(しくち)」といった伝統の技。釘やボルトを使わずに、100年たっても倒れない本堂を建てる。▽現場を率いるのは大工歴わずか7年の若き職人。京都・銀閣寺の修復にも参加した親方の元、無事、寺は建てられるのか?
2年以上にわたる密着取材の中で見えてきた彼らの木造建築にかける熱い思いに迫る。
制作局:テレビ西日本(TNC)

2014年1月19日(日)
戦争画の背景 藤田嗣治が描いた玉砕
先の戦争では、人もモノも全て動員され、あらゆるものが利用され、そのひとつに美術までも含まれていました。ある日本人画家が描いた戦争。その背景には何が?
▼東京国立近代美術館には終戦後、GHQによって押収され、1970年になって無期限貸与という他に類の無いかたちで日本に戻された絵画作品があります。153点の戦争画です。戦争画とは国威高揚と戦争プロパガンダのために、軍の要請によって書かれた「作戦記録画」のこと。中でも作品数が多いのが藤田嗣治が描いた戦争画で14点にのぼります。ヨーロッパで最も有名な日本人といわれた画家、藤田嗣治。藤田は西洋の伝統的な技法に日本の繊細な表現を融合させ、乳白色を基調とした美しい裸婦像は世界を魅了しました。1920年~30年代、日本だけでなく世界を代表する超一流の画家でした。そんな藤田も軍の要請で、戦場に赴き、戦争画を描くことになります。藤田の戦争画作品の画面は暗く、敵味方が入り乱れた凄惨な戦場に、かつて描いた美しい乳白色の世界はありません。真珠湾攻撃1周年を記念して行われた戦争美術展では380万人もの入場者数だったといいます。戦争画によるプロパガンダは確かに成功していたようです。藤田の描いた「アッツ島玉砕」が各地を巡回すると、手を合わせて拝んだり、賽銭を投げたりする客までいたといいます。先の戦争では、人もモノも全て動員され、あらゆるものが利用され、その1つに美術までも含まれていました。
制作局:テレビ西日本(TNC)

2013年12月15日(日)
大衆演劇の灯は消さねえ!旅役者・玄海竜二奮闘記
「芝居の灯は消さねえ!」北九州の小倉に新しく芝居小屋をつくる福岡生まれの旅役者・玄海竜二さんの奮闘記。果たして、こけら落としは無事にいくのか?
北九州市唯一の芝居小屋が、経営難のため28年の歴史に幕を下ろしました。かつて九州では最も身近な娯楽として親しまれていた芝居。しかし娯楽の多様化が進み、芝居小屋は徐々に減少。今では数か所現存するのみになっています。そんななか一人の男が立ち上がりました。小倉生まれの旅役者・玄海竜二さんです。「芝居の灯は消さねえ!」小倉に新劇場をつくる旅役者の挑戦を追いました。
制作局:テレビ西日本(TNC)

2013年10月20日(日)
一筆啓上
筆師・錦山亭金太夫。優しいタッチの画と人生訓を思わせる文章。素朴で味があり、どこか懐かしささえ感じさせる作品を何故この男は描くようになったのか?
商人の町・福岡市博多。飲食店ひしめき合うこの町が今、一人の男が描いた作品で溢れている。筆師・錦山亭金太夫。彼が描く作品は優しいタッチの画と人生訓を思わせる文章で、素朴で味があり、どこか懐かしささえ感じさせる。自称“遊び人”。カメラの前では飄々としていている彼が、何故このような作品を描くようになったのか?これまでの53年間の人生をさかのぼり、筆師・錦山亭金太夫の人物像を描きます。
制作局:テレビ西日本(TNC)


![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)